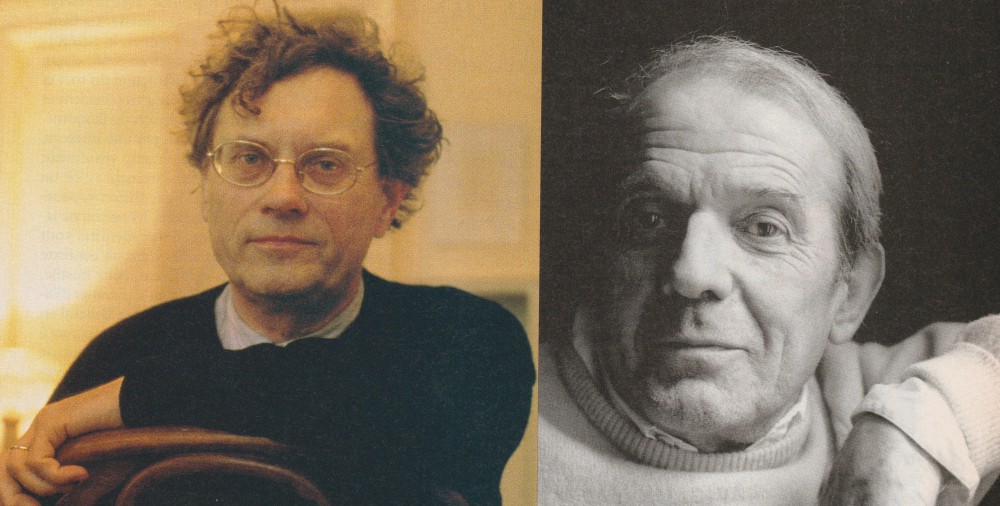2017年3月25日(土)長岡京市生涯学習センターにて、第14回DG-Lab研究会が行われました。
【読書会】『哲学とは何か』第7章「被知覚態、変様態、そして概念」(担当:小倉拓也)
小倉さんは、『哲学とは何か』を理解するための概念図式を与えるうえで、まず、そこで言及されるカオスについて理解することが重要であると指摘します。カオスとは、過飽和水溶液において結晶の核が形成されるけれどもいかなる結果ももたらさない(結晶化しない)状態があるように、いかなる成果をもたらすこともなく消散していく「誕生と消滅の無限速度」であるとされます。『哲学とは何か』は、こうしたカオスから出来し、カオスを共立的なもの、準拠づけられたもの、合成されたものへと変成させる営みを、それぞれ哲学、科学、芸術と規定します。そして、三つの営みそれぞれの生産物が、概念、ファンクティヴ(あるいは「見通し」)、被知覚態と変様態です。さらに、哲学(概念)においては「潜在的なものの実在性」が、科学(ファンクティヴ・見通し)では「潜在的なものの現働化」が、芸術(被知覚態と変様態)においては「可能的なものの現存」が論じられることになります。

Odilon Redon, “La fleur du marécage, une tête humaine et triste” (©︎The Fitzwilliam Museum, Cambridge)
ここで小倉さんは、こうした図式が『差異と反復』第2章の時間の三つの総合にゆるやかに対応しているのではないか、また、カオス概念は、『意味の論理学』における動的発生の要請(超越論的領野の発生と解体可能性の議論)と共鳴しているのではないかと指摘されました。
第7章の読解においては、自己定立auto-positionとシェリングexistenceの関連がマルディネmonument概念へと継承されたものであること、さらには小倉さんが近年とりわけ着目されている、現象学者エルヴィン・シュトラウス『感覚の意味について』、ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』の仮構概念を参照しつつ、『哲学とは何か』における芸術の議論が考察されました。
【研究発表】木元竜太「欲望的生産と社会的生産をめぐって-ドゥルーズ=ガタリとマルクスの共通項から-」
木元さんのご発表は、ドゥルーズとガタリによる『アンチ・オイディプス』を対象とし、そのなかに、マルクスの議論とドゥルーズ=ガタリとの共通項を辿ることで、社会的生産の議論に押し込められていたマルクスと欲望的生産との接線を描き出すことが目的とされました。木元さんの意図のひとつには、『アンチ・オイディプス』の政治的な側面に還元されないものとして欲望的生産の議論を取り出すことがあります。これに対しては、『アンチ・オイディプス』(ないし欲望的生産)そのものの政治性はどうなるのか、また、ネオリベラリズムが席巻する現状において『アンチ・オイディプス』を読む意義はどこにあるのかなどの意見が会場から挙がりました。『アンチ・オイディプス』は資本主義に替わるオルタナティヴを提示しうるのか、あるいは、資本主義それ自体の自己解体を暗示した書物なのかといった論点も含めて、当該図書をめぐるこれまでの研究を整理する必要があるように思われます。
(小林卓也)